英彦山の魅力
約1500年の歴史をもつ英彦山。
その歴史や魅力、近隣のオススメスポットなどを紹介します。
古来から伝わる神の山
英彦山は、約1500年の歴史を持つ修験道の聖地です。
太古には「日の子の山」と呼ばれ、自然への畏敬とともに信仰の対象とされてきました。
やがて日本最大規模の修験道の聖地となり、多くの山伏がこの地で修行を重ねてきた、
霊験あらたかな祈りのお山です。

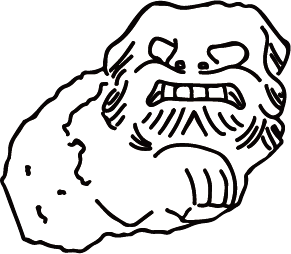
また「水分(みくまり)のお山」としても知られ、 お山から湧く清らかな水は、やがて五つの川となり、流域の自然や人々の暮らしを支えてきました。
やがてその水は、響灘、有明海、周防灘の三つの海へと注ぎ、多くのいのちを育んできました。

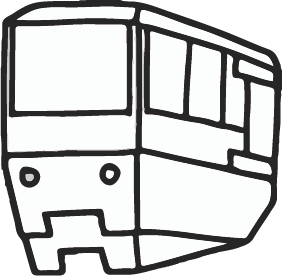
英彦山のおこり

英彦山は、古来から神の山として信仰されていた霊山で、御祭神が天照大神(伊勢神宮)の御子、天忍穂耳命であることから「日の子の山」即ち「日子山」と呼ばれていました。嵯峨天皇の弘仁10年(819年)詔(みことのり)によって「日子」の2文字を「彦」に改められ、次いで、霊元法皇、享保14年(1729年)には、院宣により「英」の1字を賜り「英彦山(ひこさん)」と改称され現在に至ってます。英彦山は、中世以降、神の信仰に仏教が習合され、修験道の道場「英彦山権現様」として栄えましたが、明治維新の神仏分離令により英彦山神社となり、昭和50年6月24日、天皇陛下のお許しを得て、戦後、全国第三番目の「神宮」に改称され、英彦山神宮になっています。
英彦山神宮の奉幣殿は740年の創建と伝わり、現在の社殿は1616年に再建された国指定の重要文化財。朱色の社殿と大鈴が迫力満点です!また400段もの石段が続く参道入口には、国指定の重要文化財である「銅(かね)の鳥居」があります。この鳥居では「英彦山」と書かれた額が見られ、これは1729年に霊元法皇に下賜されたものです。また、主祭神が太陽神(日)の御子であることから、額の裏側には太陽の丸いマークが刻まれているのもお見逃しなく!
英彦山と修験道

福岡県添田町と大分県中津市の境にそびえる英彦山は、日本三大修験山の一つです。かつては国内最大規模の修験道の聖地として栄え、約1500年の歴史があります。日本古来の山岳信仰と、密教や仏教が影響し合って、平安時代に体系化したのが日本独自の『修験道』です。かつて日本には神様と仏様を一緒にお祀りする風習(神仏習合)がありました。また修験道の修行をする者を『山伏』と呼びます。英彦山神宮は、明治時代に失われた修験道を今、再び取り戻そうとしています。


